
〜Page1〜
|
|

|
吉備国際大学大学院臨床心理学研究科 教授 |
吾郷 晋浩 |
|
NPO法人日本心療内科学会理事長 |
|
|
----------------------------------- |
|
はじめに
アレルギー疾患の診療に当たっても,その慢性化・難治化を防ぐためには、初診の段階より心身医学的な疾病モデルbio-psycho-socio-eco-ethical(medical) modelに基づくアプローチを試みることが大切であることについて述べてみたい。
なぜ心身医学的な疾病モデルに基づく医療が必要なのか
これまで、内科や小児科、皮膚科などより治療に難渋しているとして心療内科に紹介されてくるアレルギー疾患患者の病歴を、改めて心身医学的な疾病モデルに基づき取り直してみると、はじめから心身医学的な治療を行わなければ、重症化・難治化することが予想される心身症としてのアレルギー疾患であることが明らかになる場合が多い。
すでに、内科に受診してきた患者を、初診の段階で心身医学的な疾病モデルに基づく病歴を聴取し、心身両面より診断を進めると、その3割前後が心身症としての身体疾患であったとの報告がなされているが、アレルギー疾患についても同様のことが云える。
一般に、アレルギー疾患だけではなく、心身症としての身体疾患患者は、その発症機序-その発症と経過に心理社会的因子が関与していることに気づかず、あるいは認めず、それに適切に対処することなく、まわりの期待に応えようと過剰なほどに適応努力を払い続けていることが多い-より、その身体症状の苦痛が強くならない限り、社会的には適応的な行動をとっているように見えるので、まわりも-もちろん医師も-その患者が心理社会的な問題を抱えていることには気づかないし、患者自身もその心理社会的な問題を抱えていることを話題にすることは先ずないと云ってよい。
したがって、心身症としてのアレルギー疾患と診断するためには、初診時より心身医学的な疾病モデルに基づく病歴を聴取し、心身両面より情報を収集しながら心身相関を明らかにしていく必要があるわけである。
アレルギー疾患の発症と経過にみられる心身相関
代表的なアレルギー疾患とされる気管支喘息を例に、その発症状況を心身医学的な疾病モデルに基づいて見直してみると、その発症に先行して諸種の心理社会的な因子-幼小児期に発症している患者では、弟妹の出生によって生じた母親の愛情をめぐるきょうだい葛藤とそれに伴う陰性感情の処理の仕方などが、思春期・青年期に発症している患者では、進学や就職をめぐる親子関係とそれに伴う陰性感情の処理の仕方などが、成人期に発症している患者では、就職後の仕事への適性や仕事量の過重などによる過労、上司や部下との人間関係などで生じる陰性感情の処理の仕方や、結婚後の配偶者とその親族との人間関係や新しい家庭づくりに対する考え方の違いなどによって生じる陰性感情の処理の仕方など(表1)1) が加わっていることが明らかとなり、それらによってひき起こされた自律神経系・内分泌系・免疫系のバランスの崩れによる生体防御機能の低下(発症準備状態の成立)やアレルギー素質に基づく特定の神経伝達物質の遊離などによってアレルギー疾患の発症が促進されたと考えられる症例が多い。
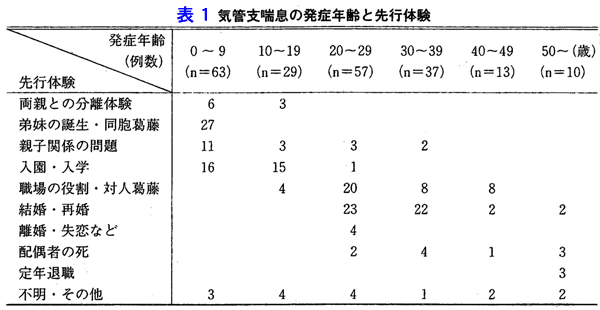 |
これらの心身医学的な臨床において観察されている現象の多くは、国内外の研究者による基礎的研究によって裏づけられている。ここでは紙数に制限があるので詳しく紹介できないが、R. Aderらの編集により1981年から10年ごとに改訂され、2001年に第3版が2巻になって出版されたPsychoneuroimmunologyに集大成されている2)。
心身医学的な診断と治療のコツ
心身医学的な疾病モデルに基づく病歴を聴取し、次のような発症状況と経過が明らかになった場合には、心身症としてのアレルギー疾患を疑って診断を進める。
|
1) |
勉強や仕事などで忙しく、息抜きや気分転換もできない生活を続けているうちに発病し、そのアレルギー症状に対応した診療科の薬物療法を受けているにも拘わらず、なかなか期待通りの治療効果があがっていない場合 |
|
2) |
生活環境や仕事内容、役割、人間関係などが変わった後に発症または増悪し、薬物療法だけではなかなかよくならない経過をとっている場合 |
|
3) |
家庭や学校、職場を離れて旅行したり、入院したりするとアレルギー症状が軽快・消失し、よくなって退院したり、学校や職場に復帰したりすると、またすぐに再燃・増悪しているような場合など |
いずれにしても、複数の心理社会的なストレッサーが加わった状況に置かれているのに、そのストレッサーを無視して、適切な対応を取っていない症例である。
心身症としてのアレルギー疾患と診断された症例に対しては、薬物療法を行いながら、面接療法(カウンセリング)、自律訓練法、行動療法・認知行動療法、バイオ・フィードバック療法、交流分析療法、精神分析的精神療法、家族療法などのいずれかを組み合わせて用いる。
|
1) |
まず、患者に合った方法で、患者がおかれているストレス状態からの解放をはかり、アレルギー症状が軽快・消失することを体験させ、心身医学的な治療への動機を高める。 |
|
2) |
心身症としてのアレルギー疾患の発症と経過に関与している諸種のストレッサーとそれに対する認知と対処の仕方を見直し、それに適切に対処できるように援助する。 |
|
3) |
アレルギー疾患の発症前後の生活習慣を見直し、健康の維持・増進を可能にする生活習慣の習得を援助する。 |
|
4) |
心身医学的な治療によって永続的な治療効果をあげるためには、誘発因子や増悪因子だけではなく、準備因子として関与している心理社会的因子に注目して、その解消をはかる治療を行うことが必要である(図1)3)。 |
|
5) |
患者に対する心身医学的治療だけでなく、必要に応じて家族や職場の人々に対しても、心身医学的な疾病モデルに基づいて、患者のアレルギー疾患の成り立ちを説明し、全人的な医療への理解と協力を得るようにするほうが、より永続的な軽快・寛解が得られることは云うまでもない。 |
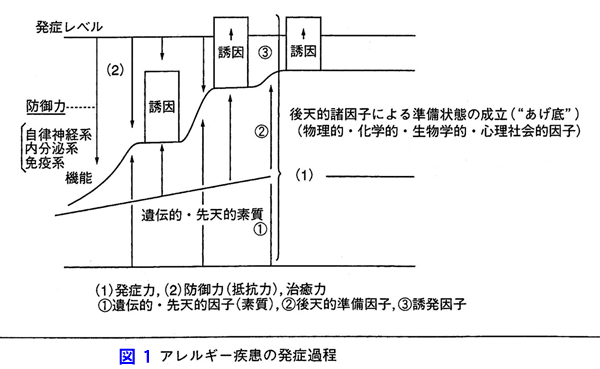 |
おわりに
アレルギー疾患の難治化を防ぐためには、初診の段階で心身医学的な疾病モデルに基づく病歴を聴取し、心身両面より検査を行い、心身症と診断された症例には早期に心身医学的な治療を行うことが必要であることについて述べた。
|
|
1) 吾郷晋浩、永田頌史:気管支喘息における心理的因子のみつけ方。 心身医療. 2:1203-1209、1990。 |
|
2) R.Ader、 D.L.Felten、 N.Cohen:Psychoneuroimmunology(3rd Ed.) Acad. Press,Inc. New York,2001. |
|
|
3) 吾郷晋浩:アレルギー疾患の心身医学的治療。 アレルギー 50:5-10, 2001。 |
|
|