
〜Page1〜
|
|
 熊本大学名誉教授 石
川 哮
熊本大学名誉教授 石
川 哮
---------------------
鼻咽喉、気管、気管支、肺という気道の
IgE
を介したアレルギー発症は、アレルゲンやメディエータに対する気道粘膜の過応答性(hyperresponsiveness)、過反応性(hyperreactivity)、過敏性(hypersensitivity)によると考えられている。
抗原暴露から発症に至る反応カスケードのいくつかのステップは、アレルゲン感作やチャレンジによって起こるアレルゲン特異的な「誘導相」と、細胞から遊離されたケミカルメディエータ、サイトカイン、ケモカインなどによって起こるメディエータ特異的な「効果相」の2相に大きく分けることができる。アレルギー反応のトリガーとなる誘導相を外的因子である抗原を回避することや内的因子である生体の反応性を免疫療法によってコントロールすることがアレルギーの治療法、予防法の基本的戦略であると云えよう。
免疫療法は、1911年 Leonard NoonとJohn Freeman によって grass 花粉症に対する花粉抽出液の注射免疫療法が最初の試みであった。未だ100年を経ていない。その有効性は、1999年WHO見解書で、的確なコントロールをおいた従来の臨床試験報告を拾い上げ、それを解析することで、ハチ毒、花粉、室内塵ダニなどに対するアレルギーに有効であることが確認された。
免疫療法の適応は、鼻炎とか喘息というアレルギーを発症している臓器がターゲットになるのではなく、「 IgE を介したアレルギー反応の修飾」である、ということもWHOの会議で再認識された。ハチ毒によるアナフィラキシーに対しては90%以上の有効率が示され、基本的治療法であり、予防法であることは世界的なコンセンサスが得られている。花粉症やアレルギー性鼻炎・結膜炎もこれに次いで有効率が高く、抗原によって差はあるが、50-80%と云われている。Engらは、5-16歳の小児花粉症に対して免疫療法を3年間行い、治療終了後更に6年間追跡で、有効性の持続が証明されている。
アレルゲンの明らかなアトピー性気管支喘息に対しては表のように有効な結果報告があるし、急速に維持量へもってゆく rush immunotherapy の喘息に対する有効性も確認されているが、殆ど喘息に対して適応はないとした時代もあり、今でもなお議論が多いのが現状である。アレルギーの早期治療・早期介入(early intervention)が唱えられ、特に喘息においては、軽症時に充分治療を行うことが勧められるようになった。Early intervention のもう1つの注目すべき効果は、小児アレルギー性鼻炎の免疫療法施行例が喘息への進展を予防できることである。Moeller らは6-14歳の小児花粉症患者205名に免疫療法を3年間行い、終了後3年間の追跡観察で喘息への進展が、免疫療法を受けなかった児に比して明らかに抑制され(odds ratio:2.52, p<0.05)、メサコリン誘発も有意に改善(p<0.05)したという報告をしている。予防法としての免疫療法の意義が見直されるべきデータである。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、わが国で免疫療法がアレルギーの治療法として普及しない原因は幾つかある。
その1つは副作用である。治療用アレルゲンの漸増注射で喘息、蕁麻疹や時に全身性アナフィラキシー誘発の危険があって、生命を脅かすという重大なリスクを伴うことが少ない疾患に対する治療法としては見合わないと考えられる現実がある。又、医療費の不採算性、通院継続に対する患者の不便性も欠点である。日本での治療用抗原の供給はもう1つの大きな問題であり、市販治療エキスは現在17種(室内塵、アカマツ花粉、スギ花粉、ブタクサ花粉、ホウレン草花粉、ソバ粉、コウジ、兎毛、羊毛、キヌ、綿、ホヤ、アルテルナリア、
アスペルギルス、カンジダ、クラドスポリウム、ペニシリウム)である。治療用ダニエキス、ペット由来アレルゲンなどは輸入によらなければならず、医療費は自己負担となる。
又、スギ花粉治療抗原は標準化されている(200AU/mlバイアル)が他は標準化がされていない。これらの問題点を解決すべく、副作用の低いアレルゲンの開発(表皮ダニやスギ花粉由来の非アナフィラキシーアレルゲン)や治療アレルゲンの投与法/ルート(経口、舌下など)の研究が着実に進められている。
免疫療法の効果発現メカニズム理論は定っていないが、アレルゲンに対する免疫応答に関わる主役 Tリンパ球のクラス(Th2)をシフト(Th1)させること、アレルゲン反応をanergyの状態に持ってゆくこと、などが現在の有力な説である。しかし、IgE 抗体量、IgG/IgG4 抗体量、Th1/Th2 など免疫応答に直接関係する治療目標となる客観的評価は確立していない。
このような実情の中でも、アレルギー治療/予防克服戦略には、免疫療法を定着させてゆく必要は益々高くなっている。非アナフィラキシー治療用抗原の開発、抗原をコードした DNA plasmid を用いた免疫療法、Th1 誘導を目的とした CpG motif など biotechnology の貢献や治療アレルゲンの投与法/ルート(経口、舌下など)の研究などに期待しながら、現状での免疫療法を臨床現場で復活させることが強く望まれる。
[文献]
1.Noon L.(1911). Lancet
I:1572-1573.
2.伊藤幸治:WHO見解書(訳)(1998). アレルギー47:749-794
3.Miller DL et al.(1971). Ann Allergy 29:178-186
4.永田真他.(1989). アレルギー38:1319-1326
5.Eng PA et al.(2002). Allergy 57:306-312
6.Moeller C et al.(2002). JACI 109:251-256
7.石川 哮(2000). The lung perspectives 18:51-56
8.石川 哮(2002). 感染・炎症・免疫 32-4:60-64
9.石川 哮(2003).
気管支喘息診療実践マニュアル:文光堂:136-140
|
PAAAプロトコール |
|
国立療養所南福岡病院アレルギー科医長 |
岸川 禮子 |
|
University of Texas Medical Branch Child Health Resarch Center Assistant Professor |
堀内 照美 |
|
----------------------------------------------------- |
|
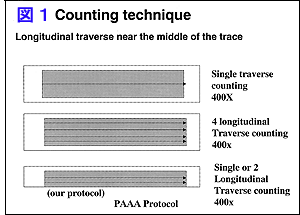 しかし、花粉症の歴史が長い欧米諸国では体積法が普及しており、これほどスギ花粉症が多く、様々の対策をとっている日本の花粉データとの比較が困難との事です。現在体積法(主に
Burkard spore trap
英国)による花粉調査は大学や衛生研究所のごく一部で行われているのみで、スギ花粉の多さからカウントの煩雑さが煩わしくBurkard
に移行するのが遅れていると言われています。今や自動計測器が出現し、ヒトの手を煩わせずに花粉がカウントできるようになりましたが、学術的にはBurkard
の成績が基本的な調査方法として必要だと思われます。
しかし、花粉症の歴史が長い欧米諸国では体積法が普及しており、これほどスギ花粉症が多く、様々の対策をとっている日本の花粉データとの比較が困難との事です。現在体積法(主に
Burkard spore trap
英国)による花粉調査は大学や衛生研究所のごく一部で行われているのみで、スギ花粉の多さからカウントの煩雑さが煩わしくBurkard
に移行するのが遅れていると言われています。今や自動計測器が出現し、ヒトの手を煩わせずに花粉がカウントできるようになりましたが、学術的にはBurkard
の成績が基本的な調査方法として必要だと思われます。
USAのAAAAIが推奨する空中花粉・真菌胞子調査方法は Burkard
7-day spore trap による調査です。USAでは現在、PAAA(Pan American
Aerobiology Association)Protocol が一般に用いられています。
PAAA Protocol は Oklahoma, Tulsa 大学のBiology Science
教室(Estelle Levetin 教授)に本部があり、Christine Rogers
氏、Michael Mulilenberg 氏によって Website
で紹介されています(webmaster@paaa.org)。
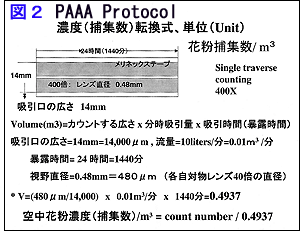 これは
Hirst trap
による空中花粉の包括的な調査方法で、その目的は多くの調査方法の最大公約数的な共通点を持ち、後から出現してくる新しい測定方法を取り入れながらさらに優秀な調査方法を目指しています。私共が最も関心があるのが
counting techinque です。
これは
Hirst trap
による空中花粉の包括的な調査方法で、その目的は多くの調査方法の最大公約数的な共通点を持ち、後から出現してくる新しい測定方法を取り入れながらさらに優秀な調査方法を目指しています。私共が最も関心があるのが
counting techinque です。
その一つを紹介します。Single longitudinal traverse( or 4 longitudinal )counting で、図1に示すようにメリネックステープのほぼ中央部を縦に一線または四線、40倍の対物レンズを用いて計数し、図2の計算方法で1m3当たりの花粉数(濃度)に換算します。蛇足ですが、真菌の胞子は1000倍でカウントします。
私共の施設で採集したスギ花粉のカウントを比較してみると(図3)、とてもよく相関しています。今後さらに相関性を検討し、実用化に向けて行きたいと思います。また Durhamの花粉捕集器による調査結果との関係も検討したいと思っています。
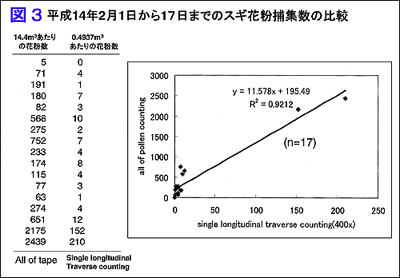
|
|