
〜Page1〜
|
|
 九州大学大学院医学研究院 心身医学 教授 久保
千春
九州大学大学院医学研究院 心身医学 教授 久保
千春
------------------------------------
はじめに
この衛生仮説は、1989年にイギリスのStrachan
博士によってアレルギーの子どもを対象とした疫学調査をもとに提唱されたもので、「衛生環境の改善や少子化にともなう乳幼児期の感染症リスクの低下がアレルギー増加の一因ではないか」というものです。
この仮説は当初免疫学的な裏付けが不十分であったことから広く受け入れられることはありませんでしたが、1型ヘルパーT(Th1)細胞や2型ヘルパーT(Th2)細胞に関する理解の深まりとともに現在では非常に注目される説となっています。
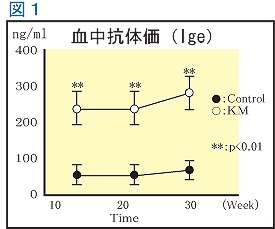 1.アレルギーとTh1/Th2バランス
1.アレルギーとTh1/Th2バランス
一般に、胎児期および新生児期の免疫応答はTh2側に偏っていて、アレルギーになりやすい状態にあると言われています。この免疫学的説明は、Th1細胞やTh2細胞など機能的なT細胞群と関連させて展開されており、これらT細胞群は異なったサイトカインの特性を示します。通常、生後発達にともなって免疫系はTh1/Th2バランスのとれたものへと移行していくことが知られていますが、免疫系の発達とりわけTh1型免疫応答の発達には、私たちを取り巻く多くの微生物からの刺激が特に重要であることがわかってきました。なかでも、感染性微生物からの刺激はTh1型免疫応答を強く誘導します。
小児期の細菌およびウイルス感染は、免疫系がTh1型へ成熟するのを誘導し、このTh1型免疫応答がTh2細胞によるアレルギー誘発応答を阻害すると考えられています(図1)。すなわち、乳幼児期にさまざまな感染症にかかることが正常な免疫機能の発達を助け、その結果としてアレルギーリスクが低下すると推察されているのです。
2.アレルギーと感染症
先進国におけるアレルギー疾患の増加は、小児期における感染症の減少によると説明されています。総微生物量の減少により、Th1型の刷り込みが弱くなり、Th2型免疫応答の抑制が外れて、アレルギー増加をきたすものと考えられています。乳幼児期に細菌由来の抗原であるCpG-モチーフと頻回に接触しなかった個体ではアレルギーを抑制する免疫細胞が発達できず、その状態がほぼ一生続くというものです。
アレルギー疾患との間に逆の相関が確認されている感染症には結核、はしか、A型肝炎、ピロリ菌感染などが挙げられます。たとえば、ツベルクリン陽性者は陰性者に比べて、アレルギー疾患罹患率が低く、Th2サイトカインの産生低下とTh1サイトカインの産生亢進が認められます。さらにツベルクリン反応陰性から陽性に転じることで、アレルギー性疾患罹患率は低下することが見出されています。また、弱毒化結核菌の接種であるBCGとアレルギー予防に関係があることが明らかにされました。
3.アレルギーと腸内細菌
アレルギーの発症に腸内細菌が関与していることが注目されています。アトピー患児では、大腸菌、黄色ブドウ菌などの好気性菌が有意に増加しており、一方、ラクトバシルス菌などの嫌気性菌は有意に減少していることが報告されています。我々の基礎研究では、生後から無菌状態で飼育した無菌マウスでは、Th1/Th2バランスがTh2優位となり、卵白アルブミンの抗原投与に対してIgEとIgG1の抗体産生が高まっていました。しかし、それらの無菌マウスへ、善玉菌として知られているビフィズス菌やラクトバシルス菌などの乳酸菌を投与するとIgEとIgG1抗体産生は、正常マウスと同じレベルになります。
一方、悪玉菌と考えられているクロストリジウム菌では、Th2優位のままでした。このように、腸内細菌の状態は、アレルギー反応に密接に影響を与えることが分かってきました。そこで、生菌製剤またはその加工物をアレルギー疾患の予防・治療に応用しようという試み(プロバイオティクス)が始まっています。現在までに発表された主な報告をします(表)。
このうち注目されるのはフィンランドのグループによるアトピーハイリスク乳児へのラクトバシルス菌による介入研究であり、ラクトバシルス菌投与によりアトピー発症が抑制されています。このように、アレルギー疾患の予防についてはプロバイオティクスの有効性が期待できますが、その一方で、すでにアレルギーを発症した成人患者に対する生菌製剤の有効性については一定の見解は得られていません。有効菌種の選定も含めて今後の課題であります。
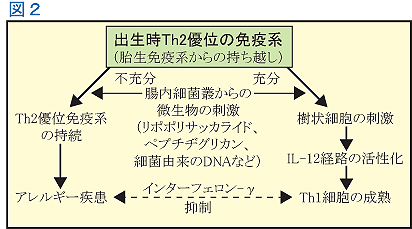 乳幼児期の抗生剤投与により成長後のアトピー発症のリスクが増加するという注目すべき報告もなされています。Farooqiらは1934名を対象に行ったretrospective研究の結果より、三つの独立したアトピー性疾患発症のリスクファクターを上げています。すなわち、
乳幼児期の抗生剤投与により成長後のアトピー発症のリスクが増加するという注目すべき報告もなされています。Farooqiらは1934名を対象に行ったretrospective研究の結果より、三つの独立したアトピー性疾患発症のリスクファクターを上げています。すなわち、