
~Page1~
|
|
 久留米大学医学部第一内科 教授 相沢
久道
久留米大学医学部第一内科 教授 相沢
久道
-------------------------------
この10年くらいの間に、気管支喘息の治療は大きく変わった。そして、吸入ステロイドを主体とするその治療の有効性は様々な形で立証されている。20年以上前に、喘息の研究をしようと思い立った頃と比べてみると隔世の感がある。しかし、すべての患者さんがこのような治療により喘息症状がコントロールされ、快適な日常生活を受けているかというと、そうでもない。
我が国においても、喘息患者の日常診療について調べた調査がいくつかあるが、それらによると、わが国の吸入ステロイドの普及率は欧米と比較してまだ低く、喘息患者のコントロールも十分とは言えないのが現状である。
アレルギー、呼吸器専門医ではほぼ欧米なみの吸入ステロイド中心の治療が行われているが、プライマリケア医における吸入ステロイドの普及が低いことが特徴としてあげられる。
我が国において、このように吸入ステロイドの一般への普及を妨げている要因はいくつか考えられる。すなわち、喘息の病態と治療に対する理解不足、ステロイドの副作用に対する不安のほか、吸入薬の服薬コンプライアンスに対する懸念から内服薬優先の思考があることなどである。
このような問題を解決し、プライマリケア医の間に吸入ステロイドを普及させなければ、多くの喘息患者が現在の進歩した喘息診療の恩恵を受けることは出来ない。喘息患者が最初に受診するのはほとんどがプライマリケア医であり、その後の管理も大多数の症例はプライマリケア施設で受けているからである。
プライマリケア医の学会としてWONCA(World Organization of
National Colleges, Academies and Academic Associations of General
Practitioners/Family
Physicians)があるが、最近WONCAが中心となり呼吸器を専門とするIPAG(International
Primary Care Airway Group)という組織を作り、GINA, GOLD, ARIA
に基づいた慢性気道疾患(喘息、COPD、アレルギー性鼻炎)のプライマリケア医を対象としたガイドラインが作成されることになった。その背景には、これらの慢性気道疾患は世界的に大きな罹患率、死亡率がありしかも増加傾向にあるため、これらの疾患に対するより良い管理が求められていることがある。
ところが、プライマリケア施設においてはガイドラインの内容を完全に実施するのは難しいため、ガイドラインが診療に活用されていないという実態がある。そこで、このような現状を変えようと企画されたものがIPAGガイドラインである。したがって、その内容はいかなる施設においてもその場に応じた実施が可能であるように作成されている。
そのために、診断手技、治療法をMinimal(最低限)、optimal(適切)、Ideal(最適)の3段階に分け、それぞれの医療環境で可能なレベルの医療を確実に施行することを勧めている。その内容を喘息を例にとって説明したい。
診断では、プライマリケア施設では必要な検査が完全に行えるわけではないので、自分たちの施設で実施可能なプライマリケア医独自の診断のための手段が必要である。
具体的には、
(1)まず患者の症状から問題を整理する(例えば、慢性気道疾患の症状として、咳は喘息とCOPDに、喘鳴は喘息に、息切れと胸部圧迫感は喘息とCOPDに、水性鼻汁と鼻の痒みはアレルギー性鼻炎に最も普通に見られるものである)。
(2)症状が慢性であることを確認する。
(3)これらの呼吸器以外の原因で起こっていることを除外する。
(4)感染性の疾患を除外する。その上で、
(5)年齢を考慮し、下記の図1に示したフローチャートを用いて鑑別診断を行う。
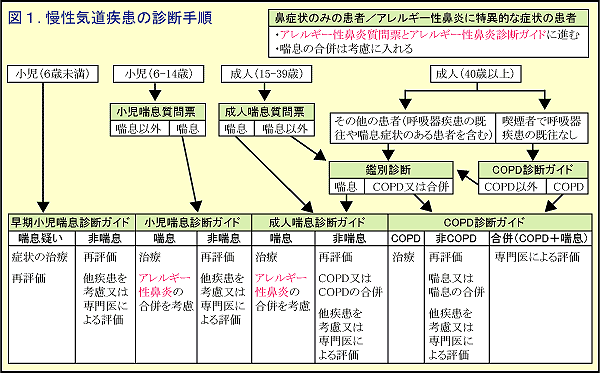
このように、まず症状に準拠し、次いで患者の年齢に応じたフローチャートにより適切な質問票とそれぞれの診断ガイドへと進み、診断を行う手順になっている。この時用いる喘息の質問票と診断ガイドを表1に示している。ここで、診断ガイドはとのようなレベルの基本設備と診断機器の施設でもその実情にあった方法が選択できるように、3段階のレベルを採用している。このような方法で診断できない患者は専門医へ紹介する。
|
表1.喘息診断の手順 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
治療においては、GINAに基づいているが、ここでも施設に応じた治療を強調するため表2のような3段階の治療レベルを示している。Minimal レベルの治療は、WHOのEssential Medicationであり、低用量の吸入ステロイドを基本とした治療である。
|
表2.重症度に応じた喘息治療 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Optimal/Ideal レベルの治療としては、低用量から高用量までの吸入ステロイドと、必要に応じた長時間作用性β2刺激薬、さらに除放性テオフィリン、抗ロイコトリエン薬、経口β2刺激薬、経口ステロイドなどの併用療法としている。
このように、本ガイドラインはあくまでもプライマリケア医がその状況に応じて最良の管理を行うためのものであるから、これらの方法でうまくいかないときは積極的に専門医を紹介するようにアドバイスしている。
プライマリケア医を対象にしたIPAGガイドラインにより、現在の進歩した喘息治療がより普遍化することが望まれる。
|
|