
〜Page1〜
|
〜QOL・ナラティブ(物語り)・患者満足度〜 |
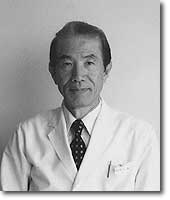
|
九州看護福祉大学大学院 看護福祉学研究科 教授 |
江 頭 洋 祐 |
|
-------------------------------------- |
|
はじめに
この数年アレルギー疾患の診療は各領域でのガイドラインの作成と普及によって、まだ十分とはいえないがレベルアップしつつあることは確かである。
今年6月に岡山で行われた第17回日本アレルギー学会春季臨床大会に参加してとくに印象に残ったことは、大会会長の国立病院機構南岡山病院の高橋 清院長の設定した「アレルギー診療のあり方」という基本テーマに沿って、アレルギー疾患の診療の質の向上を目指したシンポジュウムなどの特別プログラムが多かったことであった。
勿論、アレルギーに関する理論的エビデンスとしての遺伝子解析や免疫学的治療などについては、今回も新しくいくつかの知見が発表され、確実な進歩が認められるが、実際に臨床に応用できるまでには、意外に時間がかかるものであることも実感された。
QOL評価の意義
その中から、まずアレルギー診療の基本的課題のひとつであるQOL(生活の質)について、筆者と大阪大の荻野 敏教授で座長を務めた「アレルギー疾患のQOL評価」についてのべると、健康関連のQOLの評価はアレルギー患者さんの日常生活行動、身体症状および心理社会的状況などをトータルに患者自身の目で評価するものであり、患者を一人の生活者とみて、その主観的評価を示すものである。
QOL評価の意義としては、臨床症状に基づく全般的改善度や発作点数の動向とよく相関はするが、それぞれの領域(ドメイン)を分析すると、従来の臨床的評価では見抜けない患者自身の独自の思い(深層心理)の側面が浮き彫りになることがわかり、改めてQOL評価の意義と必要性が認識されるという報告内容があった。
医療チームでサポートする患者教育
QOLをはじめとするアレルギー診療の質の探求は、3日目に行われた公開シンポジウム「アレルギー疾患の自己管理向上のために ― 患者と医療関係者からの提言 ―」などにおいても患者教育の重要性が指摘された。
この背景としては慢性疾患の患者にありがちの自分の病状を軽くみて、セルフケアの重要性を本当に理解していない患者が少なくなく、ガイドラインの徹底不足も重なって未だに数千人の喘息死を招くなどの病状認識の不足が指摘されている。
・国際的に見れば、その面での先進国である米国では、すでにNAECB(National Asthma Education Certification Board)などにおいて、コメデイカル領域の医療従事者を対象に喘息教育者認定制度を設けて、患者指導を推進している。QOL評価のシンポジウムに特別参加したインペリアル大学のM.パートリッジ教授によると英国ではNARTC(National Asthma & Respiratory Training Center)で教育を受けた看護師らがNAC
(National Asthma Campaign)という制度においてWebサイトを使った新しい喘息患者教育を行っていることなどが紹介されていた。
日本においても半蔵門病院の灰田美智子氏とベテラン患者らによって組織されたNPO法人「環境汚染から呼吸器疾患患者を守る会」通称エパレク(Expert Patient in Respiratory Care)が活動を始めており、ここでは十分な知識と技量を有する熟練患者が新米患者の支援指導にあたっている。また、小児喘息においても「アラジーポット」などの患者支援団体が教育現場に踏み込んで活発な教育指導を進めていることが紹介されていた。
かねてから日本アレルギー協会でも「info ALLERGY」の発行や各種患者教育のキャンペーンは継続的に行っているところであり、当九州支部でも西間支部長の指導のもとにこのKKニュースをはじめ、アレルギー疾患の教育支援に関して今後ますます活動を強化し継続していかねばならない。
ナラティブ ベースド メディシン(物語り/対話の医療)の実践
・年ごとに社会における「患者中心の医療」への要求が高まりつつあるのが実感される。その流れの中で、現代科学のあまりに自然科学的EBMへの傾斜に対して、最近、医療におけるナラティブアプローチ(物語り/対話)の重要性が提唱されている。
・医療におけるNBMの実践は英国の開業医であるT.グリーンハルやB.ハーウィッツらによって1998年頃から提唱されたものであり、またたく間に世界に広がりつつある。
・NBMを要約すると、「医師は患者の"生の物語り"を傾聴し、患者の物語りと医師自身の経験知との相互交流を行い、そこから創出されてくる新しい物語による医療の構築と展開を行う」というものである。そこでは身体病としての「疾病disease」とそれに伴う患者の主観的悩みである「病いillness」の両面を十分考慮し評価することが重要になる。
・実際に喘息の診療で筆者が行っているナラティブアプローチの具体例を挙げると、外来で初診患者さんにステロイドの吸入を導入する際に、今でもやはりステロイドへの拒否感を強く持っている方に出会うことがある。そんな時こそ、とくに医師のナラティブの力が試される場面でもある。当然、患者さんの性格、知的レベルに合わせて説明するが、とくに適切な比喩の応用が効果を発揮する。つまり気道の炎症を「火事」にたとえ、発作は「炎の燃え上がり」、慢性期は「くすぶり状態、つまり火は消えていない状態」と説明し、発作はなくても火事を消すためには、抗炎症作用のあるステロイド吸入がぜひ必要だ、ということを理解させる比喩によるナラティブアプローチの実践がとても有用であると思われる。
同じく上手なナラティブの例として大阪の高槻赤十字病院の内科の安場広高部長は喘息病状の安定に必要なステロイド吸入のコンプライアンス(服薬遵守)を確実に保つ心がけとして、吸入を毎日の歯磨きに例え「皆さん毎日歯磨きはするでしょう。虫歯になってから歯磨きをしても、もう遅いですね。喘息の吸入は歯磨きと同じで、毎日予防していればひどくなることもありません。がんばって続けましょう」と誰でもわかる上手な比喩を使って「云われてする治療」から、「自ら行う治療」への転換を促そうというアプローチである。
これからは万人共通の治療ガイドラインから個別化医療の時代といわれるが、ガイドラインの普及で一定の治療レベルが確保されたら、その後は患者ひとりひとりの状況に合わせた個別の医療が求められる時代である。
しかしナラティブアプローチの実践にあたって障害になるのは、わが国の臨床では、担当医が一人の患者さんにさける時間が、あまりにも限られており、もし時間をかけても経済的な裏付がない現状では、すぐには解決できない課題である。加えて医学教育においても、患者さんとのコミュニケーションなどの人間関係的トレーニングの場がまだ少ないことも教育上の課題である。
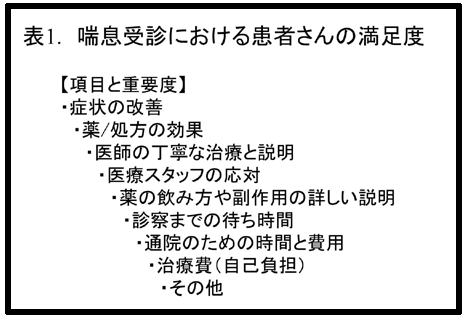
患者満足度を考える
アレルギー診療における患者のニーズは、表1に示すようなものがあり、患者さんのトータルなQOLを論じるに当たっても、診療への満足度は大きな影響があると思われる。最近ではアレルギー疾患の各診療領域における患者満足度について、いろいろなアプローチが行われている。すでに欧米では皮膚科領域で患者さんのQOLと、診療への満足度を同時に調査する研究が報告されている。
わが国ではアレルギー性鼻炎における患者満足度の調査が、奥田、大久保らによって行われている[アレルギー53(12)]。 その結果によると、診療に対する患者の満足度に影響するものは、まづは主治医との信頼関係であり、次に薬や吸入などの治療薬の効果で、3番目が医療機関の快適性や、スタッフの応対や待ち時間などになっている。
こうした流れをみていると、今後はますますアレルギー診療の、質の向上への積極的な取り組みが求められる時代になりつつあるのが感じられる。
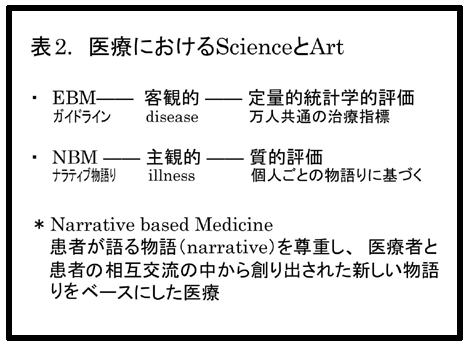
|
|