
〜Page1〜
|
|
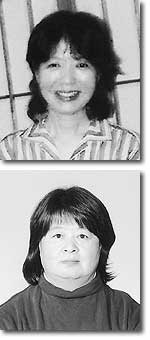
|
(独)国立病院機構福岡病院 |
岸 川 禮 子 |
|
(財)日本アレルギー協会九州支部 |
児 塔 栄 子 |
|
--------------------------------- |
|
花粉飛散情報活動は昭和63年(1988)から開始し、今年(2005年)で福岡市は17年目、福岡県は16年目、九州全域では15年目である。国立南福岡病院が、独立法人(独)国立病院機構福岡病院と名称が変更され、他の協力施設も名称やシステムが変わりながらもこの花粉情報を継続してきた。毎年協力施設の変動はあるが、約50施設が情報活動に参加されている。
今年は九州全域の花粉情報を運営している実務の方々へのアンケート調査結果を反映して2月1日から4月15日まで情報期間を延長した。又当院へ寄せられた花粉飛散情報はwebsiteで医師会の大型コンピュータに登録できるようにしていただき、省力化が進んだ。
2005年飛散の特徴は図1に示されているように、2004年に立てた予測どおり、福岡県では大量の花粉が飛散した。しかし、10年前の1995年の大量飛散年と比較すると、患者の症状は軽かったようである。また3月20日に震度6弱の地震があり、スギ花粉飛散は少なからず影響を受けたが、ヒノキ科花粉飛散には影響がなかったと考えられる。
1995年の患者受診施設と殆ど同じ施設で2005年の患者数を比較すると、患者数の増加がみられている。この増加の理由として、今年は予防対策のため早目の受診を呼びかけたことによる患者自身の自発的受診が多かったことが考えられる。
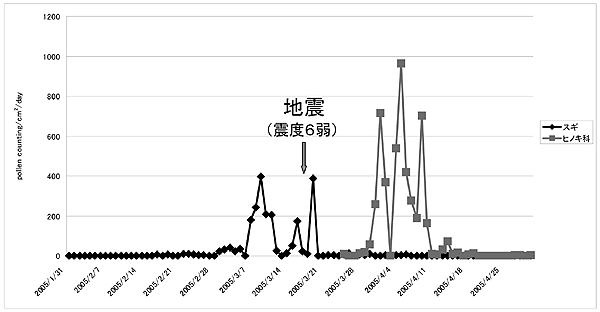 |
|
|
2005年スギ花粉飛散開始日は2月半ば過ぎであった。1995年もほぼ同じ頃で、前年10-12月の気温が高く、スギ花粉が早く開花し、1月に入って気温低下の影響もあったが、休眠期間が長期化した。この間に花粉症患者は予防治療(飛散前治療)を目的に例年より早く、多くの患者が受診したと考察できる。
スギ花粉飛散状況を総括してみると、2月19日頃飛散が始まったスギ花粉は、再び気温低下の影響で強制休眠状態になり、3月10日頃より飛散量が急増してピークを形成し、短期間に大量の飛散がみられた。飛散が後期に入った頃の3月20日に地震、その後降雨でパタリと飛散が止まった。ピーク時期には耳鼻咽喉科、眼科への受診数が急増している。
ヒノキ花粉飛散開始は、3月25日頃で、3月31日、4月1日に爆発するように急増し、4-7日にかけて非常に大量の花粉が飛散した。通常、スギ花粉の飛散期間がヒノキ科より長期で、飛散数も多いが、最近の傾向として、ヒノキ科花粉飛散量がスギを上回ることが多くなり、施設によってはスギ花粉飛散数の2倍近く捕集された。しかし、その割に受診患者数は増加していないが、飛散数が急増する前の約1週間、花粉飛散が極く僅かで症状が軽かったため、ヒノキ科花粉飛散ピーク時の症状増悪が目立った。診療に当たった耳鼻咽喉科医からは、例年のヒノキ科花粉飛散のピーク時期に比べて重症度が高い印象を受けたとコメントが寄せられている。4月12日頃より減少し始め、15日にほぼ終了した。
九州全域の花粉飛散状況としては、スギが、鹿児島、宮崎を除いて例外なく顕著に増加したのに比べ、ヒノキ科はまちまちで、ばらつきがみられた。
患者受診状況は図2に示した。福岡県の患者受診状況をまとめると、耳鼻咽喉科9施設で、9,645名、眼科4施設で、1,094名であり、昨年(2004年)の約2倍であった。前述の如く、スギ花粉飛散が始まる前からの予防的受診者数が多かったのが特徴と云えよう。
1月31日から4月16日までの耳鼻咽喉科と眼科の受診状況には有意な相関が得られた(r=0.743、p<0.001)が、花粉飛散前の予防的受診状況では両科の受診状況も有意差がみられ、眼科、耳鼻咽喉科の予防的受診も増加している(r=0.646、p<0.01)。耳鼻咽喉科受診者数が眼科の10倍であった。
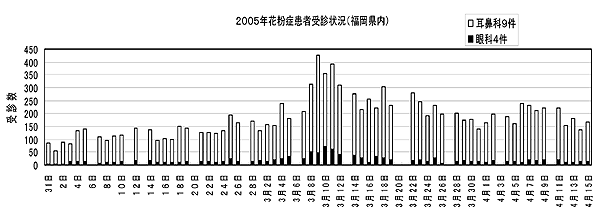 |
|
|
花粉症症状web実況サイト2005
http://kafun.jyoho-net.jp/ネットによる全国花粉症くちコミ注意報(2005年5月31日で終了したためYahooサイトからアクセス)が、(財)日本アレルギー協会と須甲松伸氏の協力によって立ち上げられた。これは日本初の試みである。
花粉症患者なら誰でも参加でき、パソコンや携帯電話から入力可能で、お互いが注意を喚起しあうことを目的としている。約70万人のアクセスがあった。アンケート調査結果は約7,000名の回答から得られ、20歳台、30歳台が約80%、男性56%であった。症状はいつから悪化したのかの質問に対し、3月上旬・中旬と回答された患者が最も多かった。治療は、病院処方薬55%、OTC
22%、治療なし23%であった。
(web siteより)
リアルタイムモニターが、2005年は20台、関東地方の花粉源と居住地区に設置され花粉飛散の動態を実況するという花粉情報提供が行われた(hanakosan)。この情報に対するアクセス数は多く、有益であったと云える。今後環境管理局大気環境課では中国・四国、九州および東北・北海道に伸ばし、平成19年までに全国を網羅して設置する予定になっている(環境省)。
しかし、未だ試用段階で、九州地区でも実用には数年かかると予想される。福岡病院では数年前から試用しているが、黄砂の影響、雪の影響、メインテナンスの困難性などの問題点を検討中である。
2006年のスギ・ヒノキ科花粉飛散予想は、当施設の捕集数から予測すると2005年7月の平均気温、平均湿度、全天日射量から予測した。それぞれ3,009, 3,126, 1,695個/cm2/seasonであり、2005年飛散数の0.24-0.44倍、過去19年間の平均飛散数(2243個/cm2/season)の1.39-0.75倍である(r=0.756、0.764、0.854、P<0.001)。来年の予測は平均数に近いと思われる。
|
|