
〜Page2〜
|
〜第36回サマーキャンプを振り返って〜 |
||
|
国立病院機構福岡病院統括診療部長 小田嶋 博 |
 今年度のサマーキャンプは、とて〜も暑い福岡から、とて〜も涼しい英彦山青年の家に出かけて行われました。少し遠かったのですが、何しろ施設の人が朝の挨拶で「今日は暑くなるとの情報です。もう朝から20度を越えていますので昼には30度になりそうです。熱射病に気を付けて行動してください」と挨拶された位で、これを聞いた我々はいたく感動しました。
今年度のサマーキャンプは、とて〜も暑い福岡から、とて〜も涼しい英彦山青年の家に出かけて行われました。少し遠かったのですが、何しろ施設の人が朝の挨拶で「今日は暑くなるとの情報です。もう朝から20度を越えていますので昼には30度になりそうです。熱射病に気を付けて行動してください」と挨拶された位で、これを聞いた我々はいたく感動しました。
さて今年度のキャンプは応募者が比較的多く、何名かをお断りせねばなりませんでした。結局子どもは募集人員通り70名。また、ボランテイアの応募も多く、約70名の応募を頂き、これもお断りをして35名にお願いしました。これに病院のスタッフ26名と合わせて、総勢131名となりました。施設の事情が許せば、もう少し多くのみなさんに参加をお願いできたのに残念でした。
ボランテイアの中には例年来て頂いている救急隊員の方が、後輩の消防隊員を連れてきたり、教育大学の学生が、クリントン君というオーストラリアの学生さんを連れてきたり(昨年に続いて、外人さんの参加)現職の看護師さんが3人、福岡大学スポーツ科学部大学院からも参加がありました。これをどこかでお読みになるかもしれませんが、本当に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。
 色々な角度から子どもに関与することができてありがたいことです。そうそう、忘れてましたが、卒後2年目の研修医も班リーダーとして頑張ってました。
色々な角度から子どもに関与することができてありがたいことです。そうそう、忘れてましたが、卒後2年目の研修医も班リーダーとして頑張ってました。
今年のキャンプの行事の新しいことは、わがキャンプで初めてのテント泊をしたこと。寝袋で寝たことです。テントの中では発作が起きるだろうと心配しました。でも、発作は起きなかったのです。また、今年は肝だめしがありませんでした。これは、本当に山の中だったので、真っ暗になるしという事情です。
そういえば、夜は鹿が啼いていました。差し入れに来てくれた師長さんは鹿と出会ったそうです。星も綺麗でした。
久しぶりに天の川を見ました。今年は星物語がなかったので、私は一人で星を満喫しました。
 久しぶりにカレーライスを作りました。私は薪割りの鉈を本当に心配しました。私のように子どもの時に鉈で薪を作った経験はない人が多く、子どもの手から目を離せず、本当に心配でした。これも何とか無事に終わりました。ウオークラリーは良く歩きましたが杉林の中はハイキング向きであったと思います。
久しぶりにカレーライスを作りました。私は薪割りの鉈を本当に心配しました。私のように子どもの時に鉈で薪を作った経験はない人が多く、子どもの手から目を離せず、本当に心配でした。これも何とか無事に終わりました。ウオークラリーは良く歩きましたが杉林の中はハイキング向きであったと思います。
喘息教室はグループ学習を取り入れ、さらに研究的に、効果的に工夫されました。喘息治療薬の進歩を十分に実際の臨床に活かすために必要なことと考えられます。
今年は最後の日に親との面接を4人の医師で行いました。、参加者のご家族から「中々行けない遠くまでありがとうございます」「子供たちが本当に楽しかったようです」などの言葉を頂きました。
喘息キャンプは、総合的医療活動として、薬物の開発が進歩した現在に於てそれを如何に効率的にきちんと使用できるか、また、小子化、核家族化の時代になって如何に子供達が自我を十分に活かし、コンプライアンス/アドヒアランスを向上させるかの点でも重要なことです。
 今後、さらに検討を加え、全国的にも実施可能な有効なキャンプ療法を確立していく必要があります。そのマニュアル作りも行うことになっています。また、福岡県全小学校に案内を配布し、福岡地区の医師会にも案内を配布しています。
今後、さらに検討を加え、全国的にも実施可能な有効なキャンプ療法を確立していく必要があります。そのマニュアル作りも行うことになっています。また、福岡県全小学校に案内を配布し、福岡地区の医師会にも案内を配布しています。
これからも、病院全体の行事として、取り組んで行きたいと考えていますので、各分野の皆様のご協力をお願いします。
また、この場をお借りして、ご協力頂きました、県、市の教育委員会、医師会、NHK、西日本新聞社、KBC、また、屋形原養護学校、東花畑小学校の皆様にお礼もうし上げます。ありがとうございました。来年度に向かって、新しい試みを行って参りますので、これからもご協力をお願い申し上げます。
|
第28回太陽の子サマーキャンプ(喘息児) |
||
|
国立病院機構東佐賀病院小児科 久田 直樹 |
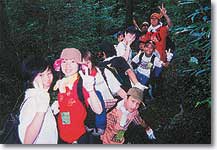 夏だから暑いのは当たり前だが今年は連日の猛暑で野外活動にかなりの影響があった。キャンプサイトの標高は約500メートルだから下界より3度くらいは低くなる。例年では夜になると半袖で過ごすと肌寒いこともあったが、今年は深夜になっても30度を超え、日当たりの良い部屋は熱がこもるためか35度に達することもあって、子供たちの睡眠不足と活動中の熱中症が心配であった。
夏だから暑いのは当たり前だが今年は連日の猛暑で野外活動にかなりの影響があった。キャンプサイトの標高は約500メートルだから下界より3度くらいは低くなる。例年では夜になると半袖で過ごすと肌寒いこともあったが、今年は深夜になっても30度を超え、日当たりの良い部屋は熱がこもるためか35度に達することもあって、子供たちの睡眠不足と活動中の熱中症が心配であった。
喘息発作への備えはもちろん、大量のスポーツドリンクと塩を持参し、団扇もこれまで以上に多く持参した(うちわも立派な医療器具!)。野外活動は少し自粛し、車の方が水分補給に走り回ってオーバーヒート気味となったが、子どもたちに熱中症の発生はなかった。
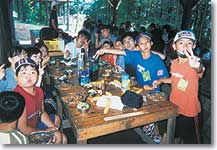 スポーツドリンクに塩を加えたものよりは乾燥梅干のほうが評判はよかった。
スポーツドリンクに塩を加えたものよりは乾燥梅干のほうが評判はよかった。
参加者21名中ICS使用者が13名、LTRAは21名中16名と割りと重症度の高いグループと思われたが、発作でβ2吸入をしたのは3人のみで、うち2人は運動誘発喘息、1名が治療不足と考えられた。
フローボリウムカーブは治療不足と考えられた1名を除いて全員が正常範囲であった。
昨年の参加者は15名と非常に少なく今後のキャンプ運営に支障を来たすのではないかと危機感を募らせていましたが、今年は予定の30名よりは少ないものの、損益分岐点ギリギリの21名となり、8月6日よりの4泊5日間は何とか乗り切れたようです。
|
〜リウマチプール教室〜 |
||
|
国立病院機構福岡病院 リウマチ科 吉澤 滋 |
 国立病院機構福岡病院では平成15年度より、リウマチ患者さんのためのプール教室を開催し、既に4年が経過しました。今回、当院のプール教室について、機会を与えていただきましたので、ここに紹介させていただきます。
国立病院機構福岡病院では平成15年度より、リウマチ患者さんのためのプール教室を開催し、既に4年が経過しました。今回、当院のプール教室について、機会を与えていただきましたので、ここに紹介させていただきます。
当院では気管支喘息患者を対象にプール療法をはじめて29年の歴史があります。特に小児を対象とした水泳教室では、大きな成果を上げてきており、現在では病院内に水泳用の25mの本格的な温水プールを備え、日々喘息の子供たちのための水泳教室が開かれています。
国立病院機構福岡病院は、前身の国立療養所南福岡病院の時に、国の政策医療として、免疫異常の分野の九州地区基幹病院と指定され、その後平成14年4月にリウマチ科が新設されました。リウマチ科では、この院内にある温水プールを利用して、平成15年より関節リウマチ患者さんを対象としたリウマチプール教室を開催することになりました。
リウマチ患者さんに対する温水プールでの運動効果としては、次のようなことが考えられています。
 筋のリラクゼーション、痛みに対する感受性の低下、筋のスパズム軽減、関節運動をより容易にする、筋力や持久力の増強、重力の軽減、末梢循環の改善、呼吸筋の機能改善、身体に対する自覚やバランスや体感安定性の改善、訓練意欲の改善と自信の回復などであり、このように多方面からの効果が期待される訳です。
筋のリラクゼーション、痛みに対する感受性の低下、筋のスパズム軽減、関節運動をより容易にする、筋力や持久力の増強、重力の軽減、末梢循環の改善、呼吸筋の機能改善、身体に対する自覚やバランスや体感安定性の改善、訓練意欲の改善と自信の回復などであり、このように多方面からの効果が期待される訳です。
特に重要なのは水温です。通常の温水プールは28-30℃前後のことが多い様ですが、リウマチ患者さんには、冷た過ぎます。入水したときに、冷たいと感じると、筋の収縮がおこり、疼痛が増し、リラックスできず、十分な効果をあげることができません。そこで34-36℃の不感温度域に近い温度が理想となります。
しかし、実際に温水中で運動をしてみると、この温度ではすぐに暑くなってしまい、1時間も続けることはできませんでした。そこで当院のプールでは33℃に設定しています。
 次にプール療法の効果に及ぼす要因は、浮力です。関節リウマチの患者さんは、足関節や膝関節に、常に体重の負荷がかかっています。ですから、運動を行う上で、常に重力による体重の負荷が関節に負担をかけ、かえって痛みを誘発することになります。しかし、水の中に入ると浮力を受けるため、膝関節や足関節にかかる体重が約10分の1に減少し、関節の負担が非常に軽減されます。膝や足関節の疼痛で歩くことが困難な患者さんが、浮力で体が軽くなっていることから、腰を落としたり、足を大きくあげたりなど、陸上ではとてもとれない姿勢での運動を、水中では容易に行うことができます。
次にプール療法の効果に及ぼす要因は、浮力です。関節リウマチの患者さんは、足関節や膝関節に、常に体重の負荷がかかっています。ですから、運動を行う上で、常に重力による体重の負荷が関節に負担をかけ、かえって痛みを誘発することになります。しかし、水の中に入ると浮力を受けるため、膝関節や足関節にかかる体重が約10分の1に減少し、関節の負担が非常に軽減されます。膝や足関節の疼痛で歩くことが困難な患者さんが、浮力で体が軽くなっていることから、腰を落としたり、足を大きくあげたりなど、陸上ではとてもとれない姿勢での運動を、水中では容易に行うことができます。
また、水中で運動をすると水による抵抗が生じ、運動に負荷がかかります。この負荷の大きさは、運動の強さあるいは速さによって変わりますので、負荷の大きさを、各自の運動能力に応じて、一回一回、自由に調節することができます。これも水中運動における効果の要因の一つです。また水圧により体が圧迫を受け、浮腫の改善、末梢循環の改善にも有効です。
 現在は、プール教室は、運営面で日本アレルギー協会九州支部の支援を受け、毎週水曜日、午後2時〜3時に開催しております。写真にプール教室の実際の様子を示しております。水中での指導は、日本水泳連盟公認のコーチ2名と、リウマチ医1名が行っています。週一回1時間、温水の中を主に歩行しています。歩行はただ歩くだけてはなく、前進、後退、横歩きなどをしながら、足を大きく上げたり腕の振りを加えたりと、いろいろな筋肉を使用する様に各自の身体能力にあわせてメニューを組んでいます。歩行距離としては、300m-500mくらいに留め、歩行距離よりも内容を重視しています。
現在は、プール教室は、運営面で日本アレルギー協会九州支部の支援を受け、毎週水曜日、午後2時〜3時に開催しております。写真にプール教室の実際の様子を示しております。水中での指導は、日本水泳連盟公認のコーチ2名と、リウマチ医1名が行っています。週一回1時間、温水の中を主に歩行しています。歩行はただ歩くだけてはなく、前進、後退、横歩きなどをしながら、足を大きく上げたり腕の振りを加えたりと、いろいろな筋肉を使用する様に各自の身体能力にあわせてメニューを組んでいます。歩行距離としては、300m-500mくらいに留め、歩行距離よりも内容を重視しています。
現在まで、18名の参加がありました。都合で、退会される方もおられましたが、どの方もみな、内容には満足していただいている様です。その中には2名ほど、杖歩行もままならない70歳代の高齢の方の参加がありました。最初はプールの中に入るのがやっとの状態でしたが、その後、次第に向上し、3-4ヶ月後には、杖をつかずに陸上を歩けるようにまで回復されました。水中で、「歩けた」と言うことが、自信にもつながっている様です。
また、この教室の前後での患者さん同士の会話は、情報交換の場にもなっており、楽しい雰囲気で行われ、笑いが途切れません。これもプール教室の効果に一役買っているようで、とても大切な時間です。集合写真をみていただいたらお解りいただけるかと思いますが、皆さんとても楽しそうです。この雰囲気を大切にしながら、週一回ではありますがこのプール教室を続けながら、プール療法の普及を目指していきたいと考えています。
|
〜小児気管支喘息児の水泳教室〜 |
||
|
国立病院機構福岡病院 小児科 本村 知華子 |
 1.
当院の水泳教室
1.
当院の水泳教室
当院の水泳教室は通称風の子会といい、小学生コース55名、3歳以上の幼児コース40名の会員を擁し、ベテランのコーチ陣と週に1回院内にあるプールで水泳訓練を行っている。今年30周年を迎え、10月の健康フェアーでは水中運動会を行った。
2. 喘息児と運動
西日本で2002年に行われた調査によると、小学生の喘息有症率は6.5%であり、小学生1クラス当たり2-3人は存在することになる。気管支喘息の誘引のひとつに運動があり、運動によって起こる喘息を運動誘発喘息という。そのため、特に体育の授業やマラソン、運動会、遠足では重症度の高い喘息児ほど参加が制限されている。
当院で毎年行っている喘息児サマーキャンプで、小学校高学年喘息児に「どんな時に喘息が起こるか」と聞くと約80%が「激しい運動のとき」と答えた。「喘息で困ることや嫌なこと」をきくと、約30%が「運動を制限されたこと」と答えた。「喘息が治ったらどんな良いことがあるか」と聞くと約40%が「思いきりスポーツができること」と答えた。このように運動制限が喘息児のQOLを低下させる大きな因子になっている。
また運動をしないライフスタイルが定着し、身体活動が低下し、その事がまた喘息を悪化させるというような悪循環に至っている。身体活動の低下は気管支喘息を悪化させるので、喘息発作を起こさずに運動を行い、小児期に運動を習慣化しておくことが大切である。
 3.
運動療法の効果
3.
運動療法の効果
多くの喘息児では運動能力が健康小児に比較し低下している。水泳をはじめとしてランニングや自転車運動などのスポーツを続けると、喘息児の心肺機能を高める。トレーニングを続けることにより運動時の換気量を減少させ、運動誘発喘息を生じにくくし、運動時の呼吸困難感を減少させることができる。運動により身体機能が向上すればするほど運動誘発喘息を起こさずに運動ができるという好循環に恵まれる。
また運動誘発喘息が軽快している喘息児では運動時のカテコラミン分泌能が改善しており、トレーニングにより運動誘発喘息が改善する機序に関与しているという結果を得ている。同時にトレーニングは気道過敏性を改善し、呼気中NO濃度を低下させ、気道炎症を軽快させることも分かってきた。
4. なぜ水泳療法か
水泳はランニングや自転車等に比べ、同じ強度の運動をしても運動誘発喘息が起こりにくいスポーツである。
その理由は以下の通りである。
|
高温多湿: |
||
|
・ |
水泳では温水により暖められ湿気を含んだ空気を呼吸することにより、運動誘発喘息での機序の一つである呼吸による気管の熱喪失を起こさず運動ができる。 |
|
|
うつぶせで運動する: |
||
|
・ |
立ち上がった姿勢より水平に寝た姿勢ではからだの中心に血流が増加し、肺への血流が増加する。 |
|
|
水泳で呼吸の量が減ること: |
||
|
・ |
水泳では水中でゆっくりと規則正しく呼吸をする。したがってランニングや自転車運動より、呼吸の数、量は水泳の方が少なくなり運動誘発喘息が起こりにくくなる。 |
|
|
水に浸かること: |
||
|
・ |
水に浸かることがからだの表面の血管を収縮させからだの中心に血液を集め呼吸による熱喪失を防ぎ、運動誘発喘息を起こしにくくする。体表面が冷やされることや、顔を水につけることが自律神経のバランスを変化させ、喘息の改善に結びついていることも考えられている。 |
|
発作が起きない強度の有酸素運動は心肺機能を高め、運動誘発喘息を減らし、喘息の症状を軽減させ、自信をつける。今後、水泳教室や教育現場で得られた知識の普及に努め、喘息児が運動する機会を増やせるようにしていく必要がある。
|
|
|
|