
乣Page俁乣
|
僞僋儘儕儉僗擃峱偺娫焄奜梡椕朄 |
|
|
|
丂傾僩僺乕惈旂晢墛乮AD乯偼丄憹埆丒姲夝傪孞傝曉偡丄憕醳偺偁傞幖怾傪庡昦曄偲偡傞幘姵偱偁傝丄姵幰偺懡偔偼傾僩僺乕慺場傪帩偮丅傾僩僺乕慺場偲偼傾僩僺乕幘姵偺壠懓楋丒婛墲楌乮婥娗巟歜懅丄傾儗儖僊乕惈旲墛丒寢枌墛丄傾僩僺乕惈旂晢墛偺偆偪偄偢傟偐丄偁傞偄偼暋悢偺幘姵乯傪桳偡傞偙偲傑偨偼IgE峈懱傪嶻惗偟堈偄慺場傪偄偆丅
AD帯椕偺奣梫偼恾侾偺偲偍傝偱偁傞偑丄墛徢偑婲偙偭偨旂晢偵懳偡傞帯椕偲偟偰偼旂怾偺廳徢搙偵墳偠偨嫮偝偺僗僥儘僀僪奜梡栻傪惓偟偔奜梡偡傞偙偲偑婎杮偵側偭偰偄傞丅偟偐偟幚嵺偺椪彴偺応偵偍偄偰偼僗僥儘僀僪奜梡偵掞峈惈偱偁傞椺偑彮悢側偑傜懚嵼偟丄偙偺偙偲偑偳偆偟偰傕僗僥儘僀僪奜梡検偺憹壛偲嬊強惈暃嶌梡偵偮側偑偭偰偄傞丅
1999擭偵僞僋儘儕儉僗擃峱偑斕攧偝傟丄僗僥儘僀僪偲偼堎側傞婡彉偱峈墛徢嶌梡傪敪婗偡傞偨傔丄椪彴偺応偱峀偔巊梡偝傟傞傛偆偵側偭偰偄傞丅
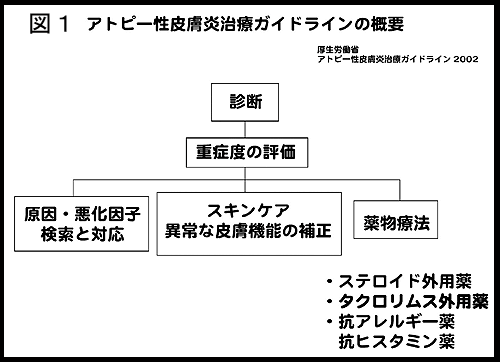
丂崱夞変乆偼丄僗僥儘僀僪擃峱丒僞僋儘儕儉僗擃峱偺娫焄奜梡椕朄偲丄僗僥儘僀僪擃峱丒曐幖嵻偺娫焄奜梡椕朄偺岠壥傪斾妑偟偰丄偦偺桳梡惈偵偮偄偰偺専摙傪峴偭偨丅徢椺偼擔杮旂晢壢妛夛恌抐婎弨偱AD偲恌抐偝傟偨17椺偱丄偦傟傜偺徢椺偺廳徢搙偑摍偟偄嵍塃懳徧晹埵傪昡壙晹埵偲偟偨丅
塃懁偵偼0.05亾棌巁僾儘僺僆儞巁儀僞儊僞僝儞傪侾擔俀夞係擔娫揾晍偟偦偺屻偺俁擔娫偼僞僋儘儕儉僗擃峱傪侾擔俀夞揾晍偟偨丅嵍懁偵偼0.05亾棌巁僾儘僺僆儞巁儀僞儊僞僝儞傪侾擔俀夞係擔娫揾晍偟丄偦偺屻偺俁擔娫偼敀怓儚僙儕儞傪侾擔俀夞揾晍偟偨丅偙偺娫焄奜梡椕朄傪係廡娫孞傝曉偟丄偙偺娫峈僸僗僞儈儞嵻撪暈傗懠偺曐幖嵻偼巊梡偟側偐偭偨丅
昡壙偼擔杮旂晢壢妛夛偺婎弨偵婎偯偒峠斄丒媫惈婜偺媢怾丄幖弫丒醥旂丒憕攋嵀丄枬惈婜偺媢怾丒戂釢壔偵偮偄偰偦傟偧傟侽乣俁傑偱僗僐傾壔偟偰昡壙偟偨丅
丂寢壥偼3偮偺昡壙崁栚偡傋偰偵偍偄偰偳偪傜偺奜梡朄傕帯椕慜偵斾傋偰帯椕屻偺僗僐傾傪桳堄偵夵慞偝偣偨乮恾俀乯丅
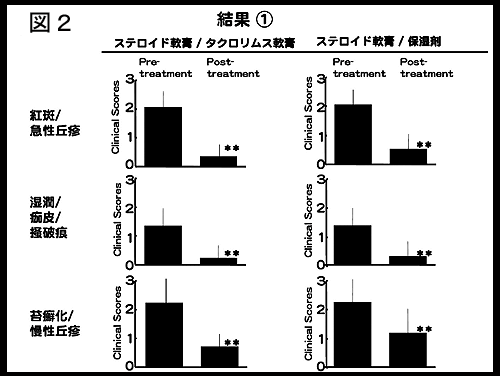
師偵旂怾偺僗僐傾偺尭彮傪昡壙偡傞偙偲偱俀偮偺奜梡朄傪斾妑偡傞偲丄峠斄丒媫惈婜偺媢怾丄幖弫丒醥旂丒憕攋嵀偺僗僐傾偵偍偄偰偼偳偪傜偺奜梡朄傕摨條偺夵慞傪帵偟偨偑丄枬惈婜偺媢怾丒戂釢壔偵偮偄偰偼僗僥儘僀僪丒僞僋儘儕儉僗擃峱奜梡偺曽偑僗僥儘僀僪擃峱丒曐幖嵻傛傝傕桳堄偵僗僐傾傪夵慞偝偣偨乮恾3乯丅
枖丄17柤拞侾柤偩偗偑嵟弶偺廡偵寉偄旂晢巋寖姶傪慽偊偨偑丄懠偺暃嶌梡偼弌尰偟側偐偭偨丅偝傜偵偳偪傜偺奜梡傪岲傓偐偲偄偆姵幰傊偺僀儞僞價儏乕偵偍偄偰偼17柤拞10柤偺姵幰偑僗僥儘僀僪丒僞僋儘儕儉僗擃峱奜梡偺曽偑椙偄偲偟丄俈柤偑偳偪傜偺帯椕傕摨條偱偁傞偲偺摎偊偱偁偭偨丅
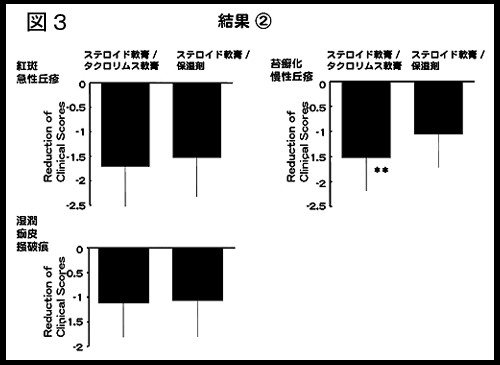
丂埲慜変乆偑峴偭偨奜梡挷嵏偱偼丄僞僋儘儕儉僗擃峱斕攧屻AD僐儞僩儘乕儖晄椙孮偑挊柧偵尭彮偟偰偄偨丅傑偨丄僗僥儘僀僪奜梡偵傛傞嬊強偺暃嶌梡偼壜媡惈偱巊梡検偺尭彮偵傛傝夞暅偡傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞偑丄僞僋儘儕儉僗擃峱傪奜梡偡傞偙偲偱僗僥儘僀僪奜梡検偑尭彮偟僗僥儘僀僪偵傛傞嬊強惈偺暃嶌梡偑偐側傝尭彮丒夞暅偟偰偄傞偙偲傕柧傜偐偵側偭偨丅
丂崱夞偺寢壥偐傜僗僥儘僀僪奜梡偼娫焄奜梡椕朄偱傕廫暘偵岠壥偑偁傝丄僞僋儘儕儉僗擃峱偲偺慻傒崌傢偣偵傛偭偰AD偵懳偟偰傛傝岠壥偑傒傜傟傞偙偲丄僗僥儘僀僪丒僞僋儘儕儉僗擃峱娫焄奜梡椕朄偱偼僗僥儘僀僪偺奜梡検傪尭傜偡偙偲偑偱偒丄偐偮僗僥儘僀僪奜梡栻偲偺慻傒崌傢偣偵傛傝僞僋儘儕儉僗擃峱偺旂晢巋寖姶傪尭彮偝偣傞偙偲偑偱偒傞偨傔旕忢偵桳梡側曽朄偱偁傞偲峫偊傜傟偨丅
崱屻傕僐儞僩儘乕儖晄椙偺AD姵幰偺尭彮傪栚巜偟條乆側奜梡朄偺専摙偑昁梫偱偁傞偲峫偊傜傟偨丅
|
|
|
|
乮撈乯崙棫昦堾婡峔丂暉壀昦堾暃堾挿
彲巌丂弐曘 |
丂乽婥摴儕儌僨儕儞僌乮airway remodeling乯乿偺梡岅偑峀偔抦傜傟傞抂弿偲側偭偨乽歜懅娗棟偺崙嵺巜恓乮Global Initiative for Asthma:捠徧GINA乯弶斉乮1995擭敪峴乯偺拞偱偼丄乽歜懅偺昦棟乿偺崁偵乽婥摴暻儕儌僨儕儞僌乮airway wall remodeling乯乿偍傛傃偦偺摨媊岅偲偟偰乽寢崌怐儕儌僨儕儞僌乮remodeling of connective tissue乯乿偑婰嵹偝傟偰偍傝丄偦偺屻丄"忋旂嵶朎偺扙棊"丄"婥娗巟暯妸嬝偺旍岤"丄"寣娗怴惗"丄"忋旂攖嵶朎偺憹惗"丄"娫幙僐儔乕僎儞偺忋旂壓捑拝"丄"擲枌壓慄偺奼戝"側偳偺慻怐曄壔傕偡傋偰乽婥摴儕儌僨儕儞僌乿乮GINA2002偵偼婰嵹偁傝乯偲偟偰岅傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偰偄傞丅暥專 1乯
丂偝偰丄娫幙僐儔乕僎儞偺忋旂壓捑拝"乮偄傢備傞乽婎掙枌偺旍岤乿乯偼丄帇妎偵慽偊傞僀儞僷僋僩傕嫮偔丄婥摴儕儌僨儕儞僌偺戙柤帉偲側偭偨姶偑偁傞丅偙偺娫幙僐儔乕僎儞偼婎掙枌偺惓忢惉暘偱偁傞嘩宆偱偼側偔丄庡偲偟偰嘨宆僐儔乕僎儞偱偁傝丄挊幰傜偺偙傟傑偱偺嵶朎梀憱幚尡寢壥乮恾侾乯偐傜偡傞偲丄惓忢側婎掙枌偺惉棫夁掱偱廳梫側栶妱傪壥偨偡婥摴忋旂嵶朎丄慄堐夎嵶朎丄寣娗撪旂嵶朎側偳偺婥摴峔惉嵶朎偺梀憱傕丄偙偺傛偆側忬懺偱偼婎掙枌壓傊偺嘨宆僐儔乕僎儞偺憹壛偵傛傝梷惂偝傟偰偟傑偆傕偺偲峫偊傜傟傞丅暥專 俀乯

丂偝偰丄恾俀偺乮敪嶌帪乯偼婥摴墛徢偑懕偔嵺偺乽婎掙枌旍岤乿偺惉棫夁掱傪帵偟偰偍傝丄岲巁媴偍傛傃慄堐夎嵶朎乮偍偦傜偔偼嬝慄堐夎嵶朎乯偐傜嘨宆僐儔乕僎儞側偳偑嶻惗偝傟丄捑拝偡傞夁掱傪柾幃壔偟偨傕偺偱偁傞丅
偙偺恾偐傜悇嶡偡傞偲丄婎掙枌旍岤偼丄寢壥揑偵偼丄忋旂攳棧偵傛偭偰奜奅偐傜偺怤擖乮僂傿儖僗丆嵶嬠傗娐嫬攋夡暔幙側偳乯偵懳偟偰柍杊旛偵側偭偨忋旂擲枌偵丄偮偔傜傟偨忈暻偁傞偄偼乽掔杊乿偺栶妱傪壥偨偟偰偍傝丄庬乆偺奜揋偐傜惗懱傪杊屼偟偰偄傞壜擻惈傪桳偡傞傕偺偲峫偊傜傟傞丅
丂偦偟偰丄偦偺偁偲偱偙傟傜偺桳奞暔幙偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨婥摴偺墛徢偑捑惷壔偡傞偲丄惗懱杊屼偝傜側傞師抜奒偲偟偰丄婥摴擲枌偼帺屓廋暅傪奐巒偡傞丅
恾俀偺乮旕敪嶌帪乯偵帵偡傛偆偵丄偦偺嵟弶偺抜奒偼丄抈敀暘夝峺慺乮僾儘僥傾乕僛乯偵傛傞乽掔杊乿偺攋夡偱偁傝丄偦傟偲摨帪恑峴偡傞宍偱丄惓忢側婎掙枌偑嵞峔抸偝傟丄堷偒懕偄偰惗偠傞婥摴忋旂嵶朎偺梀憱丒憹怋傪宱偰婥摴忋旂偑嵞惗偟偰偄偔丅
偙偺夁掱偱丄歜懅偱偺乽埆嬍乿偲偝傟偰偄傞岲巁媴傕儅僩儕僢僋僗丒儊僞儘僾儘僥傾乕僛乮MMP乯傪嶻惗偡傞側偳偟偰掔杊彍嫀偵妶桇偟丄乽惓媊偺枴曽乿偺栶妱傪壥偨偡壜擻惈偑崅偄偲昅幰偼峫偊偰偄傞丅
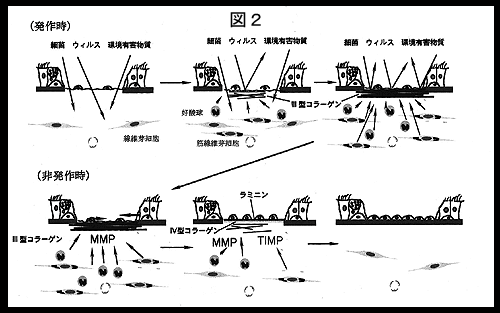
丂埲忋丄屄恖揑堄尒偲偟偰婎掙枌旍岤乽掔杊乿榑傪弎傋偰傒偨丅傕偪傠傫丄偦偺恀婾偺傎偳偑敾柧偡傞偵偼傑偩傑偩帪娫傕尋媶傕梫偡傞偱偁傠偆偑丄偼偭偒傝尵偊傞偙偲偼乽婥摴儕儌僨儕儞僌乿偵懳偟偰偼乽婥摴墛徢乿偲偼慡偔暿偺帇揰偱偺帯椕偑昁梫偲側傞偙偲偱偁傞丅偙傟傑偱偺峈墛徢椕朄偺傒偱偼側偔丄僾儘僥傾乕僛嶌梡丄偍傛傃峈僾儘僥傾乕僛嶌梡傪桳偡傞暔幙傪僶儔儞僗傛偔巊梡偡傞偙偲偑昁梫晄壜寚偵側傞丅壗傛傝傕惗懱偺帺慠帯桙椡傪忋庤偵惗偐偡帯椕傪嵟戝尷柾嶕偡傞偙偲偵側傠偆丅
惗懱杊屼婡擻傪忈奞偡傞偙偲側偔丄恀偺乽婥摴儕儌僨儕儞僌乿帯椕栻偑奐敪偝傟傞偙偲傪婜懸偟偨偄丅
|
丂暥丂專 |
|
|
侾丏 |
Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention. NHLBI/WHO workshop report. National Institute of Health. Publication No. 95-3569, 1995.乮revised 2002乯 |
|
俀丏 |
彲巌弐曘丗婥娗巟歜懅偺婎杮昦懺丂-婥摴廂弅偐傜婥摴墛徢丄偦偟偰婥摴儕儌僨儕儞僌傊-丂堛妛偺偁備傒丂210乮10乯: 804-808, 2004. |
|
丂 |
|
丂 |
